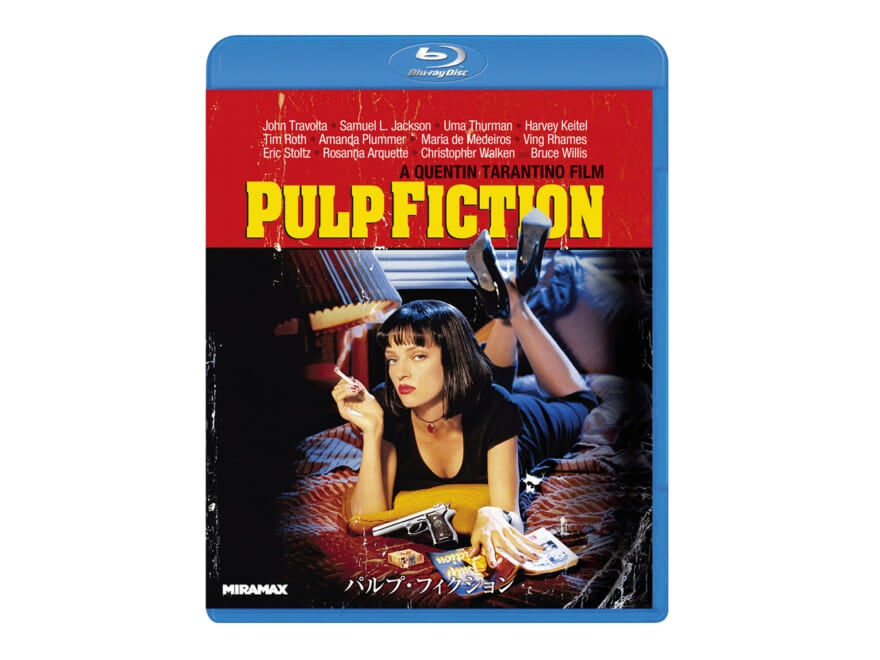▼ WPの本文 ▼

映画監督の今泉力哉が、毎回ひとつの映画のワンシーンにフォーカスし、「映画が面白くなる秘密」を解き明かす連載。
3作目
クエンティン・タランティーノ
『パルプ・フィクション』
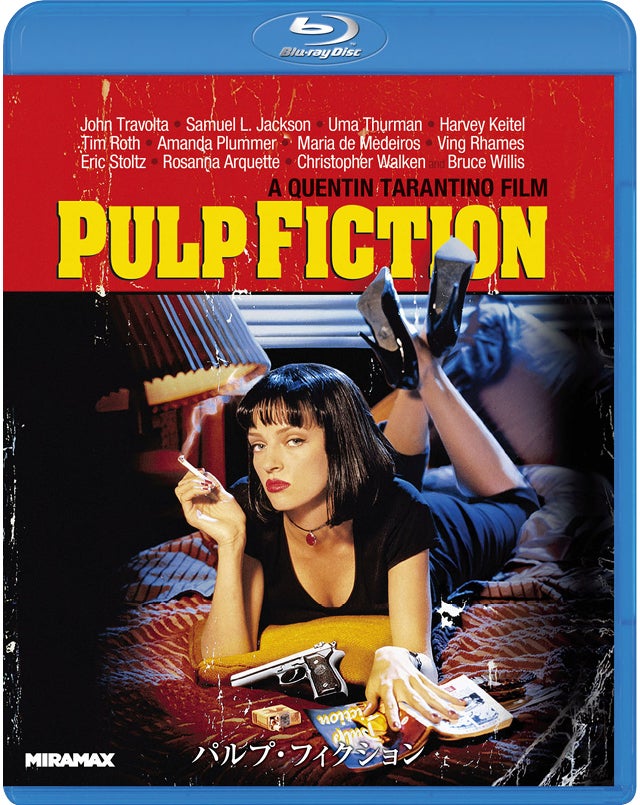
監督/クエンティン・タランティーノ 出演/ジョン・トラボルタ、サミュエル・L・ジャクソン、ユマ・サーマンほか 発売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント Blu-ray¥2,075
強盗を企てるカップルのプロローグから始まり、ビンセント(ジョン・トラボルタ)とジュールス(サミュエル・L・ジャクソン)、ブッチ(ブルース・ウィリス)をめぐる3つのエピソードを経て、プロローグと対になるエピローグに着地するクライム活劇。群像劇であるこの映画の魅力のひとつは、明確な主人公がいないこと。物語を進めるためだけの使い捨てキャラがいないところが、今泉監督の映画にも通じる。
映画が面白くなる秘密
「“無駄な時間”が愛着をもたらす」
映画なんて時間軸をいじくればだいたい面白くなるだろ。そんな安直な教訓を得てしまったのは、中学生の頃にクエンティン・タランティーノ監督の『レザボア・ドッグス』や『パルプ・フィクション』に出会ってしまったからだ。
特に『パルプ・フィクション』はカンヌでパルムドールを受賞した(でも高尚な感じがしないというのもとってもすばらしい)言わずと知れた名作です。通常の時間どおりに場面が展開せず、前後が入れ替わったりする時間軸を組み替えた構成の魅力。しゃれた映像と無駄話のようなセリフ。私も知らず知らずのうちに大きな影響を受けていて、初期の短編映画ではとにかく時間軸をいじっていました(笑)。
『パルプ・フィクション』を今回、改めて見返してみて気づいたことがあります。それはこの映画では「起承転結」でいう「転」が最後にきて、逆に「結」にあたる場面が中盤に描かれていることです。それまで主人公っぽく描かれてきた主要人物のひとりが死んでしまうシーンがあり(通常の「結」)、その後に、彼が生きている場面に戻る。つまり、顛末(てんまつ)を知っている観客は、神のような視点でその人物の人生を見つめることができるんです。そして、これ以上ない余韻を残すことができる場面で映画は終わる(通常の「転」)。結局映画とは、何を描いて、何を描かないか、そしてどう時間を切り取って見せるか、だと思うのですが、タランティーノはそれを明確に提示しています。
そうした「切り取り方」のすばらしさが顕著に表れているシーンが映画の冒頭のほうにあります。殺し屋コンビのビンセントとジュールスが、彼らのボスの所有物(詳細不明)をくすねた若造を殺しに向かう場面です。結論から言うと、彼らは部屋の中にいる若造たちを撃ち殺すことになります。しかし、そんなドンパチの少し前の場面。とてもシンプルなシーンですが、今回はここを取り上げます。
殺し屋ふたりは、予定の時間より早く着いてしまったらしく、部屋の前まで到着したのにきちんと時間を待とうとします。彼らは部屋を通り過ぎて、だらだらとくだらない話を続ける。カメラはそんな彼らの後ろ姿をとらえる。
こういう時間を、いかに映画の中に入れることができるか。どうしても通常の映画では、この無駄と思われる時間を残すことが難しいんです。そして、これは無駄な時間のようでいて、殺し屋ふたりの人間性に深みを出すのにとても重要な働きをしている。このシーンがあるからこそ、思わず彼らに愛着がわいてしまいます。
タランティーノからは、時間軸をいじる構成の妙だけでなく、こうした「無駄な時間のつくり方」についても学びました。そしてこれらはすべて、そこにいる人物が現実世界にいる人と化す方法であり、結局は「人間を描く」ということに通じているんですよね。
次回は初めて日本映画を扱います。これまた多大なる影響を受けた山下敦弘監督の初期の傑作『リアリズムの宿』。

映画監督 今泉力哉
1981年、福島県生まれ。2010年『たまの映画』で商業監督デビュー。2019年『愛がなんだ』が話題に。その後も『アイネクライネナハトムジーク』『mellow』『his』『あの頃。』『街の上で』などを発表。うまくいかない恋愛映画を撮り続ける。最新作『猫は逃げた』が3月18日に公開。
Photo:Masahiro Nishimura(for Mr.Imaizumi) Composition:Kohei Hara
▲ WPの本文 ▲